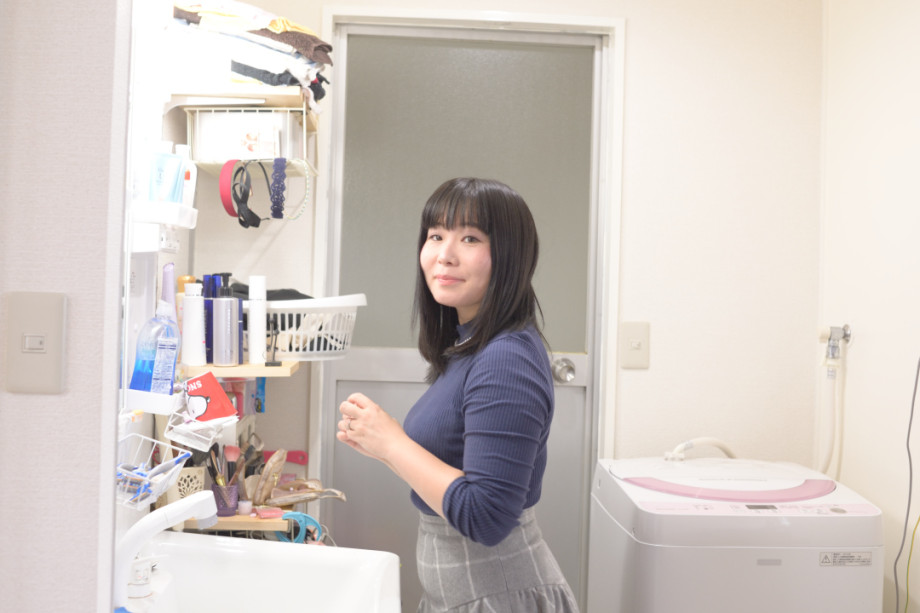11月5日、愛媛県松山市和光会館にて、The Bechdel Test 日本初演に出演しました。
(ベクデルテストの説明は、文末につけたのでわからない方は先に読むことをお勧めします)
今回の公演を終えて、自分に起こったことを書いていきます。
終わって、信頼のおける仲間たちと話をしてから気が付けたこともありました。その時系列がごちゃごちゃになっていますが、そのまま書きます。
●はじまるまえ、わたしはとてもネガティブだった
これは、終演後うつみ君が教えてくれた。「うまくできるだろうか」「これをやってしまわないか」「こんなに不安だ」フォーマットの確認段階で、わたしは信じられないくらいネガティブだった。
実は、自分でも薄々感づいてはいた。あ、ネガティブだなあ、不安でいっぱいだ。始めて取り組む、ということに対しての不安、以上に大きな不安に襲われていた。その理由はあとで考えて気が付いた。ベクデルテストを上演することで、何か、女性として、社会と闘わなくてはいけないような気持を背負っていたからだった。
●女同士の会話のシーンを演じることがとても怖い
女ふたりでシーンを作るとき、ただの飲み会とか、そういうシーンを作るのがとても怖い。男性同士の飲み会のシーンを見ても「ああ!停滞してる!なんとかしなきゃ!」とは感じない。だけど、わたしは女性プレーヤーと舞台に立って、乾杯をしたらもう怖い。何かしなきゃいけないと思う。乾杯が終わっただけでシーンが停滞していると感じる。そこで、二人の人間が、会話をしているだけでいいのに!わかっていてもまだ怖い。
だからわたしは今回焦って、焦りまくって、シーンに割り込んでしまった。本当は、そこでも会話は起きていて、しっかり、名前のついた女性が、自分の話をしていたのに、わたしの脳は勝手にそれを「ゼロ」とカウントしていた。
●わたしは宇宙工学研究をする女、ではなく、「柄本そら:宇宙工学研究員」でいられたか
今回はじめて宇宙工学研究員という職業の役を演じることができた。たぶん、普通のインプロで女性として舞台に立ったときに、職業を聞かれて「宇宙工学研究員です」とは咄嗟に言えない。保育士です、とか、主婦です、とか事務員です、とかありそうなことを言ってしまう。だからこの役が、男役としてでなくできたことはすごく嬉しかった。
このフォーマットでは、最初に名前をもらうことができる。わたしがもらったのは「宇宙大好きな、柄本そら」だった。最初の3分、わたしはただ、柄本そら、だった。だけど中盤で宇宙工学研究をしている設定がつき、宇宙工学研究員の柄本そら、になった。
終演後考えたことがある。わたしは宇宙工学研究員になったあとも、柄本そらでいられただろうか。わたしは途中から、わざと、「宇宙大好きな痛い女」にキャラを寄せてはいなかっただろうか。それはわたしの演技技術やインプロバイザーとしての器量ももちろん問題だけれど、それ以上に、柄本そら、でいることを自分で手放しはしなかっただろうか。
●わたしがベクデルテストを続けたい理由
正直に言って、わたしは実生活の中でも、インプロの舞台上でも、女であることを売りにしている。そのことだけを売りにしているわけではないが、そういう部分が絶対にある。わたしはたぶん「そこそこうまくやってる」。誰かと関わるときに、江戸川カエルとしてではなく、名前のない女として関わって来た時間がある。そのことがもたらした得がある。舞台上で名前のない女を何度も演じてきたし、そういう立ち回りのできることでやっぱり得をしたこともあった。
はじめから、できたわけじゃなかった。悔しくて泣いたり怒ったりもしたし、一時期は戦おうともした。「戦う」という気概だけで暴れまくってまわりを傷つけて、あまりうまくいかなかった。はじめからもう怒ってしまっていたから。だけど、わたしは気付いたら苦しくも辛くもなくなってしまっていた。慣れてしまっていた。怒っている女の人を見ても、もう、「そうだそうだ!」とは言えなくなった。心の中で「わたしのかわりに怒ってくれてありがとう」と思っていた。だってわたしはもう怒れない、そんな元気ないし、疲れたし。やっても無駄だし痛いフェミ女だって思われたくないし。怒っても何も変わらないのはわかっているけれど、怒らないよりマシだとはちゃんと思っていて、だけど、ほかの方法もわからなかった。
ベクデルテストでは、わたしは怒らなくてすむ。女を捨てなくてすむ。女を売りにしてきた自分を否定しなくてもすむ。戦わなくてすむ。だから誰かをひどく攻撃しなくてすむ。ただ、自分がまた、名前を失っているということに気づき続けることができる。それから見ている人も、もしかしたらそのことに気づいてくれるかもしれない。
この方法でなら、ゆっくり、わたし自身が、ジェンダーのことと向き合い続けられる。そう思った。だから、今後も続けていきたいと思えた。
【The Bechdel Testとは】
映画のジェンダーバイアスを考えるのに「ベクデルテスト」というものがある。
①名前がついている女性が2人以上登場するか?
②その女性同士が会話をするシーンがあるか?
③その会話の内容は、男についての話以外であるか?
アリソン・ベクデルの漫画に出てきたキャラクターが「これをパスする映画しか見ない!」と話している場面から「ベクデルテスト」と名付けられた。たった三つの簡単な条件だが、このテストをパスする映画は多くはない。インプロの舞台でも同様に、このテストをパスできる公演は多くはない。インプロでは、実社会よりもステレオタイプなキャラクターづくりに陥りやすいという性質上、「医者」や「先生」と聞こえれば袖で男性がスタンバイをする。そこで女性が出てくると、生徒や患者と恋に落ちるシーンになる。男性との間で上司役になったりすると、聞こえないふりされたり、陥れられたり、殺されたりする。
The Bechdel Testとは、ベクデルテストをパスするインプロを作るべく、BATSのリサ・ローランドが生み出した新しいインプロフォーマットのことだ。このフォーマットでは、3人の女性主人公が出てくる。その3人の人生のスナップショットを追っていくことができる。終演後にはアフタートークがあり、観客とプレイヤーが感じたことや思ったことを話す時間が設けられる。